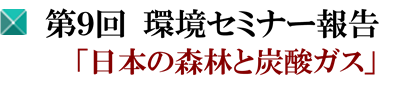| | | |
|
第9回環境セミナーは3月9日、淡交会事務局で開かれ、リモートを含め9人が参加した。
環境委員・近藤和廣(62回)の報告は以下の通り。
|
(1) |
日本の森林は荒廃していると思っている人が多いのですが、決してそうではありません。
日本の森林は、長い歴史を通じ、都市や農業に木材・肥料・燃料を提供し続けて劣化し、
江戸時代後期から明治にかけて もっとも荒廃しましたが、①燃料革命(化石燃料)、②肥料革命(化学肥料)、
③外材輸入自由化 のおかげで、木材・たい肥・薪炭の需要が減少したことと、戦後の造林努力で、
かろうじて復活し、今やかつてないほど豊かになりました。
「森林飽和」と呼ぶ人もいます。
|
(2) |
日本の国土の3分の2は森林です。
豊かになった森林を土台に 新しく導入された国連のSDGsを活かしていけば、日本の森林は
「持続可能な森林管理」と「陸の豊かさ」を実現できる可能性が、十分にあります。
北海道上川町は、森林中心の町づくりで、SDGs未来都市になりました。
海外では、超優良国家オーストリアは、林業が最先端の輸出産業になっています。
|
(3) |
近年地球温暖化で、森林が炭酸ガスを吸収する力が注目されています。
森林と炭酸ガスの間には、地球誕生・生命誕生・光合成細菌と植物の登場をめぐる長い歴史があります。
炭酸ガスと森林と温暖化の関係をよく理解することが大切です。
|
(4) |
下町5区は、大水害や大地震に備えなければなりません。
下町には森林がありませんが、そとの森林と「共生」することも考えるべきです。
|
(5) |
地球温暖化については、数百年の単位で考えれば、いままでの地球温暖化枠組条約・
京都議定書・パリ協定・IPCC・COPの考え方で進めるべきです。
すなわち、私たちは、化石燃料の排出を極力削減し、これを途上国の住民や私たちの子孫のために残しましょう。
私たちは、新しい科学の力で、太陽光や風力のほか、将来の持続可能な新エネルギーの開発に全力を傾けましょう。
|
(6) |
数万年の単位で考えれば、最後の氷期は約1万年前に終わり、次の氷期は数千年から1万年ほど
未来にはじまります。
私たちは氷期と氷期の間の間氷期に生きています。
現在起きていることは、その途中で、産業革命後、たまたまはじめてしまった化石燃料のとほうもない消費を、
森林の助けも借りながらどうやって決着させるかということです。
|
環境委員 近藤 和廣(62回)
(淡交会報第88号より転載) |
 委員会報告、セミナー報告の索引は、こちら 委員会報告、セミナー報告の索引は、こちら
|