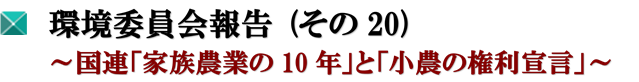|
【国連は家族農業重視に】
2017年12月の第72回国連総会で、2019〜28年を「国連の家族農業の10年」とすることが可決された。
コスタリカが発議し、日本も104か国の共同提案国に名を連ね、国際社会は、家族農業重視政策に舵を切った。
さらに、2018年12月に国連総会で、「小農の権利宣言」が採択された。
食料主権、土地や種子への権利をめぐって各国政府代表や国際NGO、農民団体、市民団体の間で攻防があったが、
最終的に、国連総会において賛成多数で採決した。
工業重視の日本は棄権した。
「小農の権利宣言」が採択されたことは、これまでの農業・食料政策を大きく問い直し、
新たな道の模索が始まったことを印象づける。
家族農業は、SDGsの中でも持続可能な社会への移行を図るためのキーともなっている。
【農業政策の戦後史】
第2次大戦後、経営規模の拡大による効率化や機械化、農薬・化学肥料の投入、新品種の導入、灌漑、
等による農業の近代化が先進国、途上国を問わず広く推進された。
1980年代以降の新自由主義では、農業近代化が、貿易自由化、規制緩和が進められ、農業補助政策は後退した。
その結果、貧冨の格差、小規模・家族農業の経営難と高齢化や離農、移民、スラム形成、貧困・飢餓、等の問題が拡大した。
その結果、政界及び学界でも、家族農業や小規模農業が再評価されてきた。
【世界の農業は家族農業】
国連では、家族農業を「家族が経営する農業、林業、漁業・養殖、牧畜であり、男女の家族労働力を主として用いて
実施されているもの」と定義している。
世界の農場数の90%以上は、家族や個人経営で、世界の農場の70〜80%で、世界の食料の80%以上を供給している。
家族農業は、食糧保障の要であり、貧困と飢餓の撲滅において、最も重要な役割りだ。
世界の貧困な人々の約40%が森林で生活し、その殆どが家族農業で、自然資源管理を行ってきた。
途上国では、農業労働力の43%が女性である。
国連は、SDGsのジェンダーの平等の観点から、家族農業における女性の役割の評価と農業女性の地位向上を訴えている。
【家族農業は非効率ではない】
これまで、家族農業は「非効率」、「時代遅れ」と見られてきたが、時代が変わり、農業に求められる役割が多様化し、
「効率的な農業」像へと大きく変化している。
【家族農業が目指すもの】
日本はいまだに、農業を日本経済や貿易自由化の「お荷物」だとする見方が根強い。
こうした評価がなされること自体、「遅れた日本」と世界から評価されている。
経済の価値は、GDPや貨幣的価値だけではなく、命の糧としての食糧供給、国土保全や環境保全、生物多様性、
景観や伝統文化・遺産の継承といった社会的・環境的価値を含んでいる。
国連で、スエーデンの高校生グレタさんが、
「人々が苦しみ、死んでいる。生態系全体が破壊され、絶滅の始まりに直面している。
それなのに、あなたたちはお金や永遠の経済成長という信じられないお伽話ばかり。
よくも、そんなことができますね」
と、世界各国首脳に訴えた言葉を再認識したい。
家族農業の10年は、農林水産業のためだけでなく、社会全体、他の生物や環境を含めた地球全体のためだ。
日本は温暖、水や緑が豊富、周囲を海に囲まれた安全な国だ。その素晴らしい豊かな自然環境を活用した農林水産業
・製造業・地元の土建業をベースにした衣食住自給率100%の国、身の丈にあった国にしたい。
|