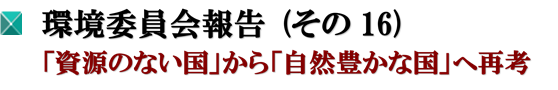アメリカのトランプ大統領が、CO2排出実質ゼロに向けた『パリ協定』からの離脱を発表した。
3号前の「淡交会報第76号」に中村晴永委員(55回)が、世界の地球温暖化対策として、先進国と途上国を含む196か国が参加し、
全会一致で、「京都議定書」に代わる、法的拘束力を持つ新たな歴史的合意が成立したと報告されたが、世界第2位のCO?排出国の
大国アメリカが、そこからの離脱をするというのだ。
その理由が取りざたされているが、
①選挙公約だった、
②TPP同様積極的に取り組んできても離脱するのがアメリカ流、
③離脱イコール環境破壊ではない、
④アメリカ経済の足かせが外せる、
等が、言われている。
ある意味、大国のエゴではないかとも評されている。
そして、日本への影響は、となると、オリンピックの2020年以降、経済大不況の到来が予想される日本経済には、
石炭などの活用が認められ、経済活性化に結び付くアメリカのいない中、日本が環境技術リーダー役になれる、
地球温暖化説を再検討する機会になる等が言われている。
CO2温暖化要因説の成否はとにかく、最近の気候変動のためか、日本や世界の災害が頻発し、
恐ろしいほどの被害を与えている感がある。
大型台風、集中豪雨、洪水、地すべり、大山火事、地震等々、今までの予想を超える凄まじい災害が続いている。
そんな中、我が家の屋上菜園では、そこそこの野菜が採れている。
会社定年ごろから本格的に始めたが、一番ありがたいことは、毎日屋上へ何回も行き来することによる運動不足解消かと思っている。
何か目的がないと運動を継続することは難しいが、野菜たちに愛情が深くなると何度も何度も行き来して、
水やりやその成長や害虫防除、鳥たちからの鳥害排除などやることが、いくらでもある。
私の住む江東区の区民農園は、毎年抽選があり、ほぼ10倍の競争率と聞く。
たくさんの方々が応募し、楽しい家庭菜園に取組んでいる。
先日東京新聞で、倉本聰さんの『田畑に向き合う徴農制の導入を』という記事を読んだ。
「若い人は土に向き合うべきだ。食うことは、生きることの根源に繋がる。江戸時代の思想家・安藤昌益は、
万人が額に汗して田畑で働く『直耕』を掲げ、孔子も孟子も釈迦ですら、知識偏重者は働かずに
観念をもてあそぶ者として拒否した。僕は男の人と会う時は、爪を見る。爪の中は黒くあるべきだ」
と語っている。
私か高校生の時代、「資源のない国」日本のこれからは、「宇宙開発・海洋開発・原子力開発」こそが、
世界の中で活躍し、生き残るための国のあり方と言われ、正月の新聞の科学特集版にその特集がなされていた。
それに乗って、海洋開発、原発開発に係ってサラリーマン時代を過ごしてきた身には、それらが今や、
ほとんど実現していないことを考えさせられる。
日本は、温暖で、雨が多く、緑が7割と世界最高級の森林率・緑被率である。さらに、山紫水明の素晴しい、
周りを海に囲まれた安全な国でもある。
その素晴らしい「自然豊かな国」の特徴を活かした国に転換することこそが、これからの課題ではないだろうか。
外国の資源に依存した国のあり方から、自分の足の下にある自然資源を活かした国のあり方、ライフスタイルこそが、
『パリ協定』に最もふさわしいものではないかと痛感させられる。
幸い日本には、埼玉県よりも大きな面積(38万ha)の耕作放棄地が広がっている。
国民1人当たりに換算すると10坪にもなる。家族で30坪にもなり、家庭菜園には適している。
今こそ「資源のない国」から「自然豊かな国」へ転換する時ではないだろうか。
|