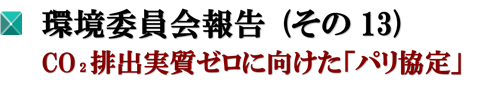2015年12月、パリで開催された第21回「国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)」で、
世界の地球温暖化対策の新たな枠組みとなる「パリ協定」が採択された。
先進国と途上国を含む196か国が参加し、全会一致で、これまでの「京都議定書」に代わる、
法的拘束力を持つ新たな歴史的合意が成立した。
「パリ協定」では、産業革命以前に比し、地球の平均気温上昇を2℃未満、1.5℃までに抑える努力目標が
明記されたこと、そのために各国は、温室効果ガス排出削減目標を自ら決め、国連に提出し、
目標達成を狙った各種の国内対策を実施することが義務付けられ、さらには、今世紀後半には、
温室効果ガスの人為的排出と吸収をバランスさせる(=実質ゼロ)ことが求められた。
削減目標自体には、法的拘束力はないものの、5年ごとの見直しが義務化され、後退は許されない、
という約束もできた。
地球の平均気温2℃の上昇が、人類の生存をいかに脅かすかについては、淡交会報第63号(2009年)の
「環境委員会報告」で、筆者は、
① 飢餓にさらされる人口の増加、
② 北極海氷や氷河の縮小、海面上昇による島の水没の危機、
③ 生態系の生存環境の破壊、
④ 森林火災、干ばつ、洪水、熱波などの異常気象が頻発する、
と述べましたが、これらが、既に現実のものとなってきた今、2℃未満に抑えることが、
ようやく全世界の共通認識となった。
これを受けて、日本政府は、2015年12月に、パリ協定を踏まえた地球温暖化対策の取組み方針を策定、
2016年3月には、環境省と経済産業省の合同審議会を経て、「地球温暖化対策計画」原案を発表した。
これによると、温室効果ガスを2030年に2013年比26%削減する目標を再確認するとともに、
その分野別削減目標(産業7%、オフィス40%、家庭39%、運輸28%、エネルギー転換28%等)を明示、
さらに、2050年までに、現在よりも80%削減するとの努力目標をも示した。
この計画案に対しては、現在、広くパブリックコメントを募集している(環境省のホームページ参照)。
再生可能エネルギーの積極的導入や原発再稼働を含めた電源構成の将来展望が、大前提となるだけに、
徹底した議論が必要だ。
 ライフスタイルの変革が必要に
ライフスタイルの変革が必要に

今後、「パリ協定」を受け、「低炭素化」「脱炭素化」の動きは、政治・経済・社会のさまざまな分野に
マイナス、プラスのインパクトを与えますが、地球の将来のために、人類はこれを乗り越えなければならない。
一例を挙げると、かねてより、「低炭素化」に熱心であったインテル、マイクロソフトなどの先進的欧米企業が、
さらに、低炭素化志向を強めることが予測されるほか、わが国でも、トヨタが2050年には、車の製造から
CO2排出車をゼロにすることを公表(トヨタ環境チャレンジ2050)、日産やホンダもこれに同調する動きを見せている。
仮に、こうした方向性が実現すれば、今世紀半ばには、化石燃料で走る車はほとんど製造されないこととなり、
部品メーカをはじめ、関連産業は、否応なしに低炭素化に向けた構造改革を迫られる。
今後、電気や化石エネルギーをふんだんに使用した便利な生活に慣れ切った私たち一人ひとりができることは、
低炭素社会の実現に向けた政治・経済の動向を監視することと、消費者としての意識改革とライフスタイル
そのものの変革に取り組むことだと考える。
|