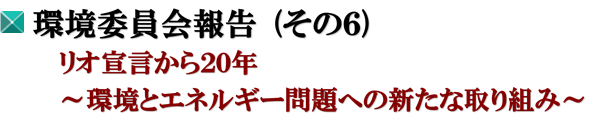|
3.11東日本大震災以降、日本社会のエネルギー問題、地球温暖化問題に関する考え方は、
大きく変貌を遂げたかに見える。
あのチェルノブイリ原発事故より深刻な東京電力福島第一原発の事故は、
安全神話を信じ込まされてきた日本人の原発に対する信頼感を一気に覆した。
また、それに伴う電力供給不足、中でも昨年実施された東京電力による計画停電は、
空気のように、使いたいときに使えるものと思っていた電気が、実は、
そうではないことを、身をもって知らされた。
原子力発電を基軸に構築されてきた日本のエネルギー政策は、当然のことながら、
3.11以降、大きく変更を迫られることになったが、事故から1年経過した今、
依然として、新エネルギー政策の全貌は見えてこない。
一方、定期試験のため稼働停止中の原発が、試験・ストレステスト終了後も
再稼働のできない状況が次々発生し、2012年5月には、54基の原発が、
すべて稼働停止状況にあるという事態が招来する。
片や、原子力発電の代替エネルギーとして脚光を浴びる再生可能エネルギーは、
いまだ全原発稼働停止を補うには程遠い状況にある。
このため、電力供給は、当面火力発電に依存せざるを得ず、化石燃料を燃やし続ける結果、
温暖化ガスの大量排出は避けられない。
これに対して、気候変動を巡る国際世論は、ポスト京都議定書においても、
温暖化ガス排出削減をめぐり、我が国に厳しい対応を迫る。
昨年12月に南アフリカのダーバンで開催されたCOP17で、ポスト京都議定書の第1拘束期間
(2012年末までに対90年比CO2排出量6%減)の延長が決まり、日本は第2拘束期間(2013年〜)
への不参加を表明したことから、2013年以降、日本は一種の空白期間に突入することになった。
これを受けて、我が国の政治家や産業界の一部に、日本は何もしないでよいというような風潮が
見られるのは見当違いも甚だしく、由々しきことである。
日本も参加した2020年までの国際合意から見れば、気候変動、特に温暖化ガスの排出量削減は
待ったなしで取り組まなければならないし、遅れれば遅れるほど、後年の国民負担が増すことは必死である。
国際的合意の一例としては、
- 工業化以前からの地球平均気温上昇を2℃未満に抑えるという長期目標を確認(カンクン合意)
- 2050年度の排出削減目標、排出量の最高値到達の時期については、COP18に向け交渉継続
- 先進国は、2020年の数値目標を実施することを約東(コペンハーゲン合意)
- 日本は、2020年までにCO2排出量を1990年比25%削減を国際的に宣言(同)
などである。
折しも、本年6月、1992年にブラジルのリオディジャネイロで開催された「地球サミット」から、
丁度、20年の節目に当たるのを機に、同市で「地球サミット」(リオ+20)が開催される。
100か国に及ぶ各国政府首脳やNGO、NPOが、さまざまな提案をもちより、
持続可能な地球について話し合う記念の年である。
3.11大災害からの復興はまだ緒に着いたばかりの日本は、先のCOP17では、
ポスト京都議定書からの離脱が、それほどの抵抗感もなく容認されたようだが、
この先も先進国の一員として果たすべき責務を放棄するようでは、国際的失望感は
少なくないものと思われる。
政府・経済界の重い腰を上げさせるのは、一般市民や消費者であり、
これからの社会をになう若者である。
地球温暖化防止に積極的でない政治や企業に、はっきりと「NO」と決別を宣言し、
選挙で投票しないし、そういった企業の商品・サービスを買わない、という覚悟が必要ではないか。
なお、政治家や産業界に注文を付けるだけでなく、日常的にも、地球人の一人として、
家庭や職場で節電・省エネを実践し、持続可能な社会づくりに少しでも貢献したいものだ。
淡交会環境委員会は、メンバーの活動を通じて、「環境とエネルギー問題」への研究と実践を重ね、
今後とも、環境委員会報告や両国祭の淡交会展示「地球環境展」などで、訴求していきたい。
一緒に活動していただける会員各位は、事務局にご一報ください。
|